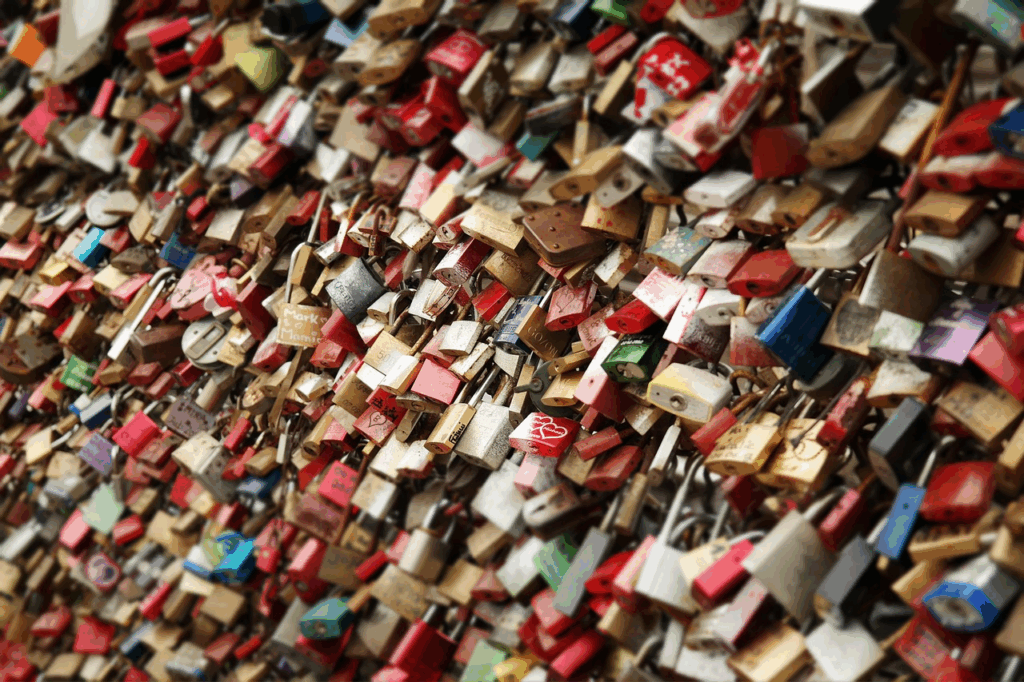
結婚を考えるとき、愛情と同じくらい大切になるのが「お金」の話です。特に「私たちの収入で、将来ちゃんと貯金できるのかな?」という不安は、多くのカップルが抱える共通の悩みではないでしょうか。
そこで今回は、ごく平均的なモデルケースとして「夫の年収300万円・妻の年収250万円」、つまり世帯年収550万円の共働きカップルを想定。この二人が結婚してから5年間で、どれくらいの貯蓄ができるのかを、ライフイベントを考慮しながら具体的にシミュレーションします。
結論からお伝えすると、このカップルは計画的に家計を管理すれば、5年間で500万円以上の貯蓄を形成することも、決して夢ではありません。この記事では、その具体的な道のりを、年を追いながらリアルな数字で解説していきます。
前提条件:世帯年-収550万円カップルのプロフィール
シミュレーションの前提となる、二人のプロフィールを設定します。
- 収入(手取り):
- 夫:年収300万円 → 手取り年収 約240万円(月20万円)
- 妻:年収250万円 → 手取り年収 約200万円(月16.7万円)
- 世帯の手取り月収:約36.7万円
- 年間ボーナス(手取り):夫婦合計 約60万円
- 生活環境:
- 都心から少し離れた、神奈川県や埼玉県などの賃貸マンション(1LDK)で同棲スタート。
- 極端な節約はしないが、無駄遣いはしない堅実なライフスタイル。
【1〜2年目】共働き時代の「黄金の貯蓄期」
子どもがいない共働きの期間は、人生で最も貯金がしやすい「黄金の貯蓄期」です。ここでいかに貯蓄ペースを確立できるかが、将来を大きく左右します。
【1〜2年目の家計簿モデル(月間)】
- 収入(手取り):36.7万円
- 支出:
- 家賃:9.0万円
- 食費:4.5万円
- 水道光熱費・通信費:2.5万円
- お小遣い(夫婦各3万円):6.0万円
- 保険・医療費:2.0万円
- その他(交際費・趣味など):3.0万円
- 支出合計:27.0万円
この場合、月々の貯金額は9.7万円。これを2年間(24か月)続けると、 9.7万円 × 24か月 = 232.8万円 これに2年分のボーナス(60万円×2回=120万円)のほとんどを貯蓄に回せたとすると、 232.8万円 + 120万円 = 352.8万円
2年間で、約350万円の貯蓄が可能です。この時期に家計簿アプリなどで家計を「見える化」し、二人で協力する習慣をつけることが重要です。
【3〜4年目】出産と育休――収入減をどう乗り越えるか
結婚3年目に、第一子が誕生したと仮定します。妻は産休・育休に入り、世帯収入は一時的に減少します。
- 収入の変化: 妻の収入は、健康保険や雇用保険からの給付金(出産手当金、育児休業給付金)に変わります。これは、おおよそ元の給料の50%〜67%程度。世帯の手取り月収は、夫の収入と合わせて約28万円に減少します。
- 支出の変化: おむつやミルク、ベビー服などの子ども関連費用で、支出は月3万円ほど増加します。
この時期の月々の貯蓄はかなり難しくなりますが、黄金期に築いた貯蓄があるため、赤字にならずに生活を維持することが目標になります。この2年間は、夫のボーナス(手取り約40万円×2回=80万円)を堅実に貯蓄に回すことで、 352.8万円 + 80万円 = 432.8万円 4年目の終わりには、貯蓄額は約430万円に達します。
【5年目】妻の仕事復帰と、見えてくる「500万円」
5年目、妻が時短勤務などで仕事に復帰します。
- 収入の変化: 時短勤務により、妻の手取り月収が約12万円になったとすると、世帯の手取り月収は約32万円まで回復します。
- 支出の変化: 認可保育園の保育料として、月3万円の新たな支出が発生します。
この時期の月々の貯金額は、約2万円ほどになります。 2万円 × 12か月 = 24万円 これに、回復した夫婦のボーナス(手取り合計約50万円)を加えると、5年目の1年間で約74万円の貯蓄が可能です。
最終的に、5年間の合計貯蓄額は、 432.8万円 + 74万円 = 506.8万円
シミュレーションの結果、5年間で500万円を超える貯蓄を形成することができました。これは、将来のマイホーム購入の頭金や、子どもの教育資金として、大きな安心材料になるはずです。
今回のモデルはあくまで一例ですが、世帯年収550万円という条件でも、計画的な家計管理と夫婦の協力があれば、着実に資産を築けることがお分かりいただけたかと思います。大切なのは、まず「黄金の貯蓄期」を逃さないこと。そこから、二人で未来を見据えたチームプレーを始めてみてください。


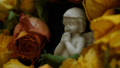
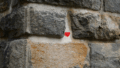
コメント