
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 初デートの雰囲気は良かったはずなのに、なぜか次のお誘いを断られてしまう男性
- 「会話は弾んだのに…」と、女性からのフェードアウトに悩んでいる男性
- 女性が初デートで男性のどこを、どのように見ているのか、その本音を知りたい人
- 次こそは本命の女性との関係を一歩先に進めたいと本気で願う、すべての男性
- 自分のデートの何がダメなのか、客観的に知りたい男性
「今日のデート、すごく楽しかったです!またぜひ!」
初デートの別れ際、彼女は確かに笑顔でそう言った。会話も弾んだし、店も気に入ってくれたみたいだ。手応えは十分。そう確信して、数日後に「また近いうちに食事でもどう?」とLINEを送る。しかし、返ってきたのは「ごめんなさい、最近ちょっと忙しくて…」という、誰がどう見ても脈ナシのテンプレ回答。
…こんな経験、あなたにもありませんか?
もし、あなたがこの状況に「なぜ?」と本気で首をかしげているのなら、残念ながら、あなたは恋愛における最も重大で、そして最もありがちな”勘違い”の沼にどっぷりと浸かっています。
この記事では、なぜ「盛り上がったはず」のデートが2回目に繋がらないのか、その残酷な真実を、一切のオブラートに包まずに解説していきます。厳しい内容になるでしょう。もしかしたら、あなたのこれまでの努力を全否定することになるかもしれません。しかし、この現実から目をそらさない限り、あなたは永遠に「1回会って終わる男」のままです。覚悟して読み進めてください。
大前提:会話が盛り上がった=成功、という大いなる勘違い
まず、あなたのその甘い認識を、ここで叩き壊しておく必要があります。 それは、「会話が盛り上がったから、デートは成功だ」という、致命的な勘違いです。
多くの男性は、デートの成否を「会話がどれだけ弾んだか」で測ろうとします。沈黙の時間がなければOK、相手がたくさん笑ってくれたら成功、と。しかし、それはあまりにも浅はかで、自己中心的な判断基準です。
思い出してください。女性という生き物は、多くの場合、あなたよりも遥かに高いコミュニケーション能力と社会性を持っています。彼女たちが、初対面の相手に対して笑顔で相槌を打ち、楽しそうに話を合わせるのは、あなたに好意があるからではありません。それは、その場を円滑に進めるための「社交辞令」であり、波風を立てないための「処世術」なのです。
あなたが気持ちよく自分の話をしている間、彼女の頭の中では、冷徹なまでの”査定”が行われています。あなたが「今日の俺、イケてたな」と悦に入っているその裏で、彼女は心の中で静かに「あ、この人はないな。次はない」と、無慈悲な判決を下しているのです。
会話が盛り上がったように見えたのは、単に彼女が大人の対応をしてくれただけ。あなたは、ただ彼女の優しさの上で、気持ちよく踊らされていたに過ぎないのです。この残酷な現実を、まずは受け入れてください。そこが全てのスタートラインです。
女性はここを見ている!2回目を決める”減点ポイント”
では、女性は一体、デートのどこを見て「アリ」か「ナシ」かを判断しているのでしょうか。男性が「加点法」で相手のいいところを探そうとするのに対し、女性は多くの場合、「減点法」で相手を評価します。つまり、致命的なミスを犯した瞬間に、即刻「ナシ」のフォルダに振り分けられるのです。
あなたが無意識にやらかしている、2回目のデートへの扉を完全に閉ざす”致命的なミス”を具体的に見ていきましょう。
致命的ミス1:尋問スタイルの質問攻め 「ご趣味は?」「休みの日は何してるんですか?」「好きな食べ物は?」…沈黙が怖くて、矢継ぎ早に質問を繰り返していませんか?これは会話ではなく「尋問」です。女性は、面接官に根掘り葉掘り聞かれているようで、ひどく疲弊します。「私のことを知ろうとしてくれている」のではなく、「ただ沈黙を埋めたいだけなんだな」と見透かされています。
致命的ミス2:自分の話ばかりするプレゼン大会 学歴、仕事の功績、持っている知識、過去の武勇伝…。聞かれてもいないのに、自分の有能さをアピールするような話ばかりしていませんか?女性が求めているのは、あなたの自己紹介プレゼンテーションではありません。その自慢話は、あなたの魅力を高めるどころか、「自信がない人なんだな」「器が小さい男」という最悪の印象を与えているだけです。
致命的ミス3:致命的な段取りの悪さ 行く店を予約していない、店までの道順を把握しておらずウロウロする、会計時にもたつく…。これらの段取りの悪さは、一発で「頼りない人」という烙印を押されます。それだけではありません。「私とのデートを、大して重要視していないんだな」「大切にされていない」という、強烈なメッセージとして彼女に伝わってしまうのです。
致命的ミス4:ネガティブ発言と他者批判 仕事の愚痴、上司や同僚の悪口、店の料理への文句。これらのネガティブな発言は、デートの空気を一瞬で凍りつかせます。聞いているだけで気分が滅入りますし、「この人は、いつも何かのせいにして生きているんだな」「一緒にいても、絶対に楽しくない」と、将来性がないことを確信させてしまいます。
これらのミスに、一つでも心当たりはありませんか?もしあるなら、それがあなたの「次がない」根本的な原因です。
なぜそのミスが”致命的”なのか?女性心理の深層
これらのミスが、なぜそこまで「致命的」なのか。それは、女性がデートという場で、無意識のうちにあなたの「生存能力」と「遺伝子としての資質」を厳しくチェックしているからです。
少し生物学的な話をしますが、女性は古来、自分と、そして生まれてくる子供を守り、育ててくれるだけの能力を持ったパートナーを選ぶようにプログラムされています。デートは、そのための極めて重要な「適性検査」の場なのです。
・段取りの悪さは、計画性のなさ、つまり「生存能力の低さ」を示唆します。いざという時に、この人は私や子供を守るための準備や行動ができないのではないか、という本能的な不安を掻き立てます。
・自分の話ばかりする自慢癖は、自己中心性であり、「協調性の欠如」を意味します。子育てという共同作業において、この人は自分のことしか考えず、協力してくれないのではないか、という警戒心を生みます。
・尋問スタイルの会話は、相手の気持ちを察することができない「共感性の低さ」の表れです。心を通わせ、精神的な支えとなるパートナーとしては不適格だと判断されます。
・ネガティブ発言や他者批判は、「精神的な不安定さ」の証明です。ストレス耐性が低く、困難な状況を乗り越える力がないと見なされ、共に人生を歩むパートナー候補から即座に除外されるのです。
あなたがやっていることは、単なるデートでの失敗ではありません。進化の過程で女性に刻み込まれた「危険なオスを回避する警報システム」を、自ら大音量で鳴らしているようなものなのです。
データが示す「次がない男」の悲しい現実
これも、私の妄想ではありません。数々の調査データが、この現実を裏付けています。
ある大手マッチングアプリが女性ユーザーを対象に行った「初デートで『もう会いたくない』と思った男性の行動」というアンケートでは、以下のような項目が常に上位を占めています。
1位:「店員への態度が悪かった」(58%)
2位:「自分の話ばかりしていた」(55%)
3位:「食事のマナーが悪かった」(49%)
4位:「デートプランがノープランだった」(42%)
注目すべきは、「会話が面白くなかった」という項目は、これらよりもずっと下位に位置しているという事実です。つまり、女性は男性が思っている以上に、会話の”中身”そのものよりも、あなたの「人としての在り方」や「他者への配慮」を鋭く観察しているのです。
別の婚活支援サービスの調査では、初デート後に女性が交際を断る理由として、実に7割近くが「性格や価値観の不一致」を挙げており、その中身を詳しく見ると「気遣いが感じられなかった」「頼りないと感じた」といった、デート中の振る舞いに関するものが大半を占めていました。
これらのデータが示すのは、男性が必死に磨いている「トークスキル」や「面白い話のネタ」が、実は二次的な問題でしかないという、あまりにも皮肉な現実です。
結論:『楽しませる』から『安心させる』へ。視点を変えろ
では、どうすれば「次がある男」になれるのか。 結論を言います。今すぐ、「女性を楽しませよう」という発想を捨ててください。
あなたが目指すべきは、面白い話で彼女を爆笑させる「エンターテイナー」ではありません。細やかな配慮と揺るぎない安定感で彼女を包み込む「ガーディアン(守護者)」なのです。
女性が本能的に求めているのは、刹那的な「楽しさ」ではありません。この人と一緒にいれば大丈夫だ、という根源的な「安心感」です。
・この人は、私のことを大切に扱ってくれるだろうか?
・この人は、いざという時に頼りになるだろうか?
・この人と一緒にいて、私は心からリラックスできるだろうか?
2回目のデートへの扉を開く鍵は、この3つの問いに、あなたの”行動”で「YES」と答えることです。
面白い話ができなくてもいい。スマートなトークができなくてもいい。それよりも、店をきちんと予約しておくこと。彼女が話しやすいように、聞き役に徹すること。車道側をさりげなく歩くこと。別れた後に「無事に着いたか」と気遣うLINEを送ること。
そういった一つ一つの地味で小さな配慮の積み重ねこそが、女性の心に「この人は信頼できる」という、何物にも代えがたい「安心感」を育むのです。
視点を180度変えてください。「楽しませる」から「安心させる」へ。 そのパラダイムシフトこそが、あなたを「1回で終わる男」の呪縛から解き放つ、唯一の道なのです。


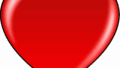
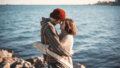
コメント